★あらすじ
「古鎮」とは、歴史ある街並みを残す中小規模の地方都市や村落のこと。「老街」とは、街に古くから残る通りを指す。本書は、著者が中国各地の古鎮・老街を訪れて書き記した紀行文だ。しかし、多くの古鎮は商業主義のディベロッパーによって観光地としての開発権を買い占められ、住民は追い出され、元々の街並みは壊されて擬古様式の画一的な建物に建て替えられてしまいつつある。そんな状況の中でも著者は各地に残る歴史的な建造物や、その土地独特の風俗を探しだし、書き残している。
河北省懐来県鶏鳴駅は北京から列車・バスを乗り継いで三時間半ほどにある旧宿場町だ。かつて八つの古寺・廟があったが文化大革命などで破壊され、荒れ果てた状態らしい。この街は、西太后が西安へ逃れる途中に訪れたことがあることで知られている。文官たちはみな逃げ出してしまったが、賀という武官が街に残っていて、西太后を迎え入れてもてなした。と言っても、粟の粥と卵だけだったが。と、宿の主人は自慢げに著者に話してくれた。
重慶市南岸区下浩老街は長江の東南岸に広がっている。かつて、長江の船舶輸送の港として栄え、十九世紀末には国民党が拠点を構え、米英仏の公使館も置かれた。そのため、外国の建築様式を取り入れた建造物も多く建てられ、大いに栄えた。しかし、港町としての歴史的使命を終えた2000年頃からは再開発に備えて住民も立ち退き、寂れて行ってしまった。しかし、ネット上でその歴史的価値が知られるようになると多くの若者が訪れるようになり、新たに喫茶店やアトリエなどが増えていく。と言っても、街並みは残されたものの、かつての地元民はほとんどが去ってしまったが。
★基本データ&目次
| 作者 | 多田 麻美 |
| 発行元 | 亜紀書房 |
| 発行年 | 2019 |
| ISBN | 9784750516127 |
| 写真 | 張全 |
- はじめに
- 1章 キャラバンの通った道
- 2章 埠頭でつながる港町
- 3章 脈々と続く伝統文化
- 4章 商人たちの汗と涙
- 5章 開発と保護の狭間
- 6章今と昔の交差点
- 7章 信仰が支えた町
- 8章 消えがたい戦の記憶
- あとがき
★ 感想
私が最後に中国へ行ったのは2019年。重慶を仕事で訪れました。その時の中国は景気も良く、高層ビルがガンガン建設され、昔ながらの街とおぼしき場所はもうなくなってしまっていた感じでした。さらに昔、2009年に北京を訪れた時には胡同(北京市の旧城内を中心に点在する細い路地のこと)めぐりができたのですが。
著者は大学で中国語を学び、中国へ留学もしたそうで、語学は堪能。地元の人々とコミュニケーションが取れるという強みを持っている(まあ、多くの古鎮で“強い”方言に苦戦したようだが)。単に観光地を紹介するだけではない、土地の歴史や人々の営み、そして直面している“観光地化”の問題など、ルポルタージュと呼べる内容となっている。ポツンと残る店にふっと入っていき、年老いた店主から昔話を引き出す。街の歴史に対する誇りと共に、廃れ行く街への寂しさが彼らとの会話から伝わってくる。臨場感があり、まさにそこに訪れたような気分にさせてくれた。
私が旅行した時はもちろん中国語でのコミュニケーションはできず、英語の通じる観光地の店以外は観て回るだけだった。私が見た街並みは本当に古くからあるものだったのか、擬古様式で建てられた新しいものだったのかよくわからないままだ。特に地方を旅するのであれば語学は必須なのかもしれない。
と思う人が多いと分かっている著者は本書冒頭で「空想の中で古鎮を旅する読者の助けになれば」と語ってくれている。ありがたいことだ。
「中国四千年の歴史」というものの、さすがにそんな昔のものは残っていないよう。それでも明代の石畳が残っていたりするそうだから、日本で言えば室町時代の街並み(の一部)が見られるのは凄い話だ。日本ではせいぜい「江戸の街並み」程度だろうから。
中国語を勉強して、自分もそんな古鎮を巡ってみたいものだが、最近の中国はきな臭い話が多いし、難しそう。本書で旅気分を味わうだけにしておいた方が無難そうだ。
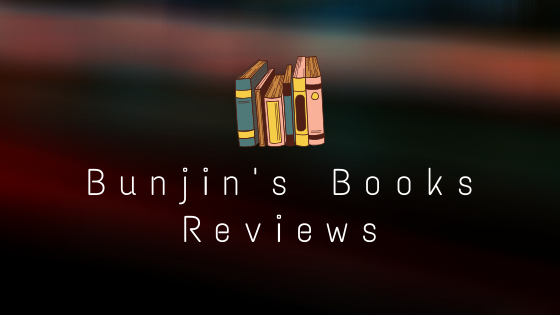



コメント