★あらすじ
「論語」の中で孔子は自らを卑賤に生まれついたせいで転々と半端仕事をこなしながら食いつないできた、と語っている。孔子世家でも「孔子は品にして且つ賤」と記す。「史記」には魯の定公が宰に任命したなどとあるが、牧場の小役人だった孔子が上級行政官に一挙に昇格するとは考えられず、この記述は信用できない。孔子は生涯を通じてまともな官職に就かなかった可能性が高い。
孔子は三代の礼制を知り尽くしているとの自負心から、魯に清王朝を草子遷都する妄想を抱いた。しかし、卑賤の出である孔子は王朝儀礼はおろか、諸侯や卿・大夫の家で行われていた儀礼すら、ろくに目撃できない境遇だった。かくして、失意の中、孔子は生涯を閉じる。
孔子の死後、弟子たちは孔子の“妄想”を虚構の中に実現しようと奔走し始める。孟子は「実は孔子は王者であった」とする偽装工作を始める。経書(過去の王たちが記した書物)の「春秋」は実は孔子の著作だった、王者五百年周期説から孔子は新王朝の開祖たれと天の啓示を得た聖王だったのだ、などなど。
前漢末から後漢にかけてはさらに孔子に宗教の教祖たるに相応しい神秘的権威を与えようとする運動が盛んになる。講師の母・顔徴在は夢の中で黒帝と交わって孔子を出産したとして、聖母マリアの処女懐胎に類する生誕神話を捏造した。
劉邦が漢を興すと、国家組織の整備が当面の急務となる。儒家はこの機を捉えて礼楽の専門家として売り込み、ついには国家の中枢に勢力を伸ばしていったのだ。
★基本データ&目次
| 作者 | 浅野裕一 |
| 発行元 | 講談社(講談社学術文庫) |
| 発行年 | 2017 |
| ISBN | 9784062924429 |
| 原著 | 儒教 ルサンチマンの宗教 |
- 学術文庫への序文
- 序
- 第一章 孔子という男
- 第二章 受命なき聖人
- 第三章 まやかしの孔子王朝
- 第四章 神秘化される孔子
- 第五章 孔子、ついに王となる
- 第六章 儒教神学の完成
- 終章 ルサンチマンの宗教
- あとがき
★ 感想
儒教に関しては断片的にしか知らず、「論語」や「大学」、「中庸」などは全く読んだことがなかった。また、儒教はやたらと実践的で現世の倫理を説き、神などについてはあまり語られていないんじゃないかとの印象を持っていたので、果たしてこれが“宗教”なのかもよく知りませんでした。
ということで、入門として書名だけを見て手に取ったのでした。
が、本書は儒教に関しての解説書ではあるけど、かなり(極端に?!)異端の書だったようで、これを一冊目の入門書として読んでしまったのは希有な体験だったかも知れない。
サブタイトルに「怨念と…」とあるけど、本書の著者こそが儒教に対して恨みがあるんじゃないかと言うほどの論調。
孔子は卑賤の出で、官職に就いたことはなく、当然ながら王朝儀礼など知る由もなかった。そのくせ、過去の聖人達の業績を盗み、自分は王になるべき存在だと信じて疑わない“トンデモ”な存在で、最期まで己の不遇について恨み辛みをぐちぐち言いながら死んでいった。。。
という調子だ。
孔子は紀元前六世紀頃の人だから、実際にどんな人だったのか、どんな生涯を送ったのかは後世の人々の伝えるところからしか分からない。そのため、著者のように解釈することも可能なのだろう。
宗教の創始者なんてそんなものかもしれない。キリストだってユダヤ教における異端で、最期まであちこちを弟子たちと放浪していて生涯を終えた。彼自身が“聖書”を執筆した訳ではなく、後世の弟子や信奉者たちが神へと祀り上げた、とも言える。
ブッダにしても、妻子を捨て、国の政務を放り投げて自分の悟りを開こうとした自己中心的な奴、と言えなくもない。
逆説的だが、その意味では儒教も確かに宗教なのかも知れない。創始者が偉大すぎると一代で終わってしまうけど、隙だらけで大雑把なことだけを語っていた方が、それに続く者たちは好きに話を盛ることができるのだろう。そして、結果として後世の我々からみても「なるほど、良いことを言っている」という優れた思想体系を作り上げることができたのだろう。
いやぁ、面白かった。宗教をテーマにした書籍なのに、読むのが止まらないほどだった。
とは言え、孔子がどういう人物だったかどうかは別にして、現在までに伝わっている「論語」をはじめとした儒教の教えがどんなものなのかは別に学ぶ必要がありそうだ。
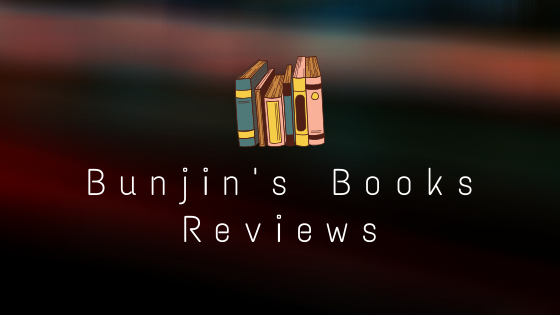



コメント