★あらすじ
Y字路はなんかいい。道が鋭角に分かれているとその角は「残余地」として様々な「都市の漂流物」が堆積する。
まち歩きには「路上の目」と「地図の目」、そして「表彰の目」の三つの視点がある。実際に自分の目でY字路を眺めるとそこには石碑や自動販売機、電話ボックスなど様々なものが置かれている。一方、地図で確かめていくとなぜY字路が生まれたのかが見えてくる。地形の起伏や河川の存在などによって生み出されていったことがわかってくる。さらに、歌に歌われるY字路や絵画に描かれるY字路には人々が抱くイメージがそこに込められている。
地図の目でY字路を見ると、なぜそんな道ができたのかが見えてくる。そして、その発生理由の違いから街道系Y字路、地形系Y字路、開発系Y字路、グリッド系Y字路に分類できる。
例えば街道系Y字路だと、主要な二本の街道の分かれ道、いわゆる“追分”と言われる地がY字路となるのだ。
京都市左京の吉田はY字路が多い。京都といえば「碁盤の目」のイメージがあるが、なぜ吉田の街はこんなにも錯雑としているのか。一つの要因は川の存在だ。北から南に流れる鴨川に対して上流の高野川は斜めになっている。また、今は暗渠になっているが農業用水路だった太田川がウネウネと蛇行していたのだ。その後の都市計画における区画整理も吉田には適用されずに今に至り、結果としてY字路だらけの街となったのだ。
★基本データ&目次
| 作者 | 重永瞬 |
| 発行元 | 晶文社 |
| 発行年 | 2024 |
| 副題 | 本邦初!街の見方がまったく変わる「Y字路学」の第一歩 |
| ISBN | 9784794974457 |
- はじめに
- 一章 Y字路へのいざない
- 二章 Y字路の姿 ― 路上の目
- 三章 Y字路はなぜ生まれるのか ― 地図の目
- 四章 Y字路が生むストーリー ― 表象の目
- 五章 Y字路から都市を読む ― 吉田・渋谷・宮崎
- 六章 Y字路とは何か
- おわりに
- 主要参考文献・出典
★ 感想
本書でも語られているが、横尾忠則の描いたY字路のシリーズは私も好きだ。街を散歩していてY字路に出会うと、なんでこんな区割りになっているの?と知りたくなってしまう。また、Y字路の地に建つ三角形のビルを見つけると必ず写真を撮ってしまう。間違いなくY字路は魅力的だ。
著者は大学院に通う研究者とのこと。そのためか、ちょっと論文調の記述になっている。お蔭で論理的でとてもわかりやすい文章になっている。三つの視点でY字路を解説しているが、各視点で分類を定義し、それぞれの例を写真入りで示している。文章だけだとイメージしにくいものも写真があるので「ああ、確かにこういうY字路、見たことあるな」という感じで納得できる仕組みだ。
それにしてもここまで細かく分類しているとはさすがです。そして、自分が見たことのあるパターンが出てくると「祠のあるY字路、近所にもある」となって、親近感がさらに増してきた。きっと、この分類パターンを暗記しておくと、今後の街歩きがもっと楽しくなるだろう。どうせならGoogleマップにY字路を登録しつつ、分類もマークしていこうかな。って、もう誰かやっているだろうか。
研究書っぽいと言う点では、著者はちゃんとその土地の歴史を調べ、Y字路が形成された理由を推察しているところもいい。私も京都の吉田や、渋谷の道玄坂・宇田川町辺りは馴染みがあったけれど、そんな歴史があったとは知らなかったことも多く、とても興味深く読めた。「ブラタモリ」でタモリさんが街の高低差から過去の土地の様子を推測する場面がよくあるが、あの気分が味わえた。
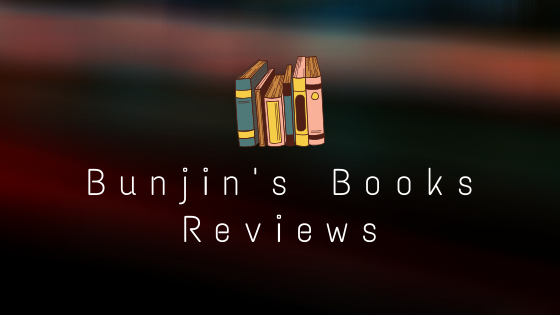



コメント