★あらすじ
本書は科学に関する文章の書き方の本である。研究費の申請書や報告書、雑誌やウェッブサイトの記事執筆などでが対象となるが、他の分野でも論理的な文章を書くときには役に立つだろう。
本書が扱うのは「読者」がいる文章である。そのため、「読者のことを考えること」がまず必要である。そのためには「読者が誰かを考える」必要がある。研究費申請書ならば審査官であり、新聞記事などでは不特定多数の人が読者と考える。読者が不特定多数の場合、具体的な読者をイメージしてはいけない。豊かな多様性を持つ日本語だが、不特定多数向けの文章はその一部しか使ってはならず、窮屈なものである。「読者が誰かを考える」とは、読者の①知識と②目的を考えることだ。文章を書く際に間違いやすいのは②目的の方だ。
世の中には内容が「分かる文章」と「分からない文章」がある。また「分かり易い文章」と「分かりにくい文章」がある。例えばノーベル賞作家大江健三郎の評論は「分かる文章」だが「分りにくい文章」だ。本書は「分かる文章」かつ「分かり易い文章」を書くことを目指している。大江健三郎の文章を分かりやすくしてしまうと、あのかっこよさは消えてしまうだろう。しかし、本書ではかっこよさは求めない。
また、「正確さ」と「分かりやすさ」は相反する概念だ。論理的な文章を分かりやすくすると正確さが失われる。正確さを失わない範囲でいかに分かりやすくするかの努力が問われることになる。
そのためにはまず、「文は短く」することだ。個人的な印象では、だいたい80字以内に収めればよいと思う。文が長くなったときは短い分に切り分ける必要がある。そしてその際、切った文の順序を入れ替えたほうが良いこともある。入れ替えに問題ないかは語調で判断すれば十分だ。書いた文章を必ず読み返してチェックするようにしよう。
★基本データ&目次
| 作者 | 更科 功 |
| 発行元 | 講談社(ブルーバックス) |
| 発行年 | 2020 |
| 副題 | 今日から役立つ科学ライティング入門 |
| ISBN | 9784065195628 |
- はじめに
- 第1章 読者
- 第2章 論理と接続
- 第3章 わかりやすい文章
- 第4章 パラグラフ・ライティング
- 第5章 科学ライティング
- 第6章 科学と社会の架け橋
- おわりに
★ 感想
文章を書くのは難しい。どうしても独りよがりになってしまう。そんな点を反省せねばと思ったときには科学論文や、本書のような“理系”向け文章術の本を読むのがいいと思っている。それは、本書の冒頭でも強調しているように「読者」を意識して書くことを思い起こさせてくれるからだ。
もちろん小説や随筆も作家たちは読者に向けて書いているだろう。だが、小説の書き方指南の本はなんというか、“上級者向け”という気がしてしまう。基本を理解した人がさらに自分の文章に個性を持たせつつ、より読者に“訴える”、読者の“琴線に触れる”技を伝授しようとしている感じがするのだ。残念ながら、私はまだその域には全くたどり着いていない。
本書は、論理的かつ読者に誤解をさせずに自分の考えを伝えるための文章術を述べている。そのため、本書の文章自体も“楽しい読み物”というよりは、教科書的な雰囲気の文体だ。しかし、読みにくいわけではないのが面白い。論理はスッキリしているし、例示も分かりやすい。本書自体が、本書で推奨している文章術に則って書かれているのだから当たり前かもしれないが。その意味では、本書を読んで分かりやすいと思えたら、本書で推奨している文章術が自分なりに理解できたということを示しているのかもしれない。
長くなるので上記の「あらすじ」では割愛してしまったが、本書では「パラグラフ・ライティング」について詳しく述べられていて、論理的文章の書き方の基本だと訴えている。その歴史から始まり、例を示しつつこの手法の基本ルールを順に説明してくれていてとても分かりやすい。
- 一つのパラグラフでは、一つのトピックだけを述べる。
- キーセンテンスはパラグラフの最初に書く。
などのルールが11項目に渡って述べられている。
章の終わりには基本ルールの一覧を再掲してくれている親切さだ。
私も普段、この手法を実践しているつもりだったが、改めて基本ルールを確認し、もっとブラッシュアップできることを痛感した。
このブログでもいろいろな「文章術」の本を紹介したが、本書もまた読むべき一冊に加えたい。特に、自分の文章を“すっきりさせたい”と思っている人にはおすすめです。
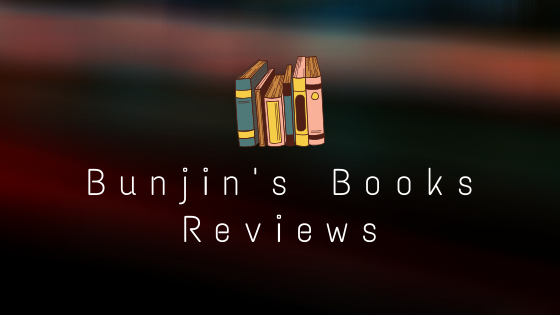



コメント