★あらすじ
椿井政隆(1770-1837)は江戸時代中期の山城国の人。偽文書、偽由緒書、偽系図・偽絵図を大領に作成し、近江、大和、河内の各地から大量に見つかっている。村々が土地争いを起こしたり、神社の格を争ったりした際、自分たちの主張の“根拠”として「昔からここに書かれている・描かれている通りです」と“古文書・絵図”の類を持ち出す。そんな文書・絵図などを作り出していたのが椿井政隆だったのだ。
例えば、津田村と穂谷村との係争の際には、津田山にあったとされる津田城の縄張り図や、その領主である津田氏の家系図などを作っている。“関連文書”があると信憑性が高まってくる仕掛けだ。
さらには、室町時代の文書そのものだとなると見た目でバレてしまうので、古文書の“写し”もしくは“写しの写し”だとして、紙や墨などの物理的なものの新しさを隠し、内容のみに注目させるようにしている。有印公文書(私文書)偽造として非常に高度なテクニックが施されている。
そんな偽書に騙された、振り回されたのは当時の人々だけではない。現代の歴史研究者や、市町村の史跡保存に携わる人たちも椿井文書を信じ込んでしまい、自分たちの論文に組み込んでしまったり、史跡紹介の看板を建ててしまったりしている。
もちろん、これらが偽文書であると見抜いた学者も少なくなかったが、いちいちそれを報告することはなく、単に「使えない資料」として自分の研究活動から外してしまうだけの場合がほとんどだ。そのため、椿井文書を信じてしまう研究者があとを絶たない。
本書はそんな椿井文書の総合的研究を行った成果である。椿井文書の作成過程や流布の仕方、許容されていく状況などを順に明らかにしている。
★基本データ&目次
| 作者 | 馬部隆弘 |
| 発行元 | 中央公論社(中公新書) |
| 発行年 | 2020 |
| 副題 | 日本最大級の偽文書 |
| ISBN | 9784121025845 |
- はじめに
- 第一章 椿井文書とは何か
- 第二章 どのように作成されたか
- 第三章 どのように流布したか
- 第四章 受け入れられた思想的背景
- 第五章 椿井文書がもたらした影響
- 第六章 椿井文書に対する研究者の視線
- 終章 偽史との向き合いかた
- あとがき
- 参考文献
★ 感想
「歴史は勝者が作る」とはよく言われることで、時の為政者が自分の都合のよいように歴史を書き換えてしまうということ。後世の我々はその点をよくよく考慮して歴史を考えなければならない、という戒めだ。本書の主人公である椿井政隆も、ある意味では“勝者”なのかも知れないが、こんなパターンの歴史改ざんもあるのかと驚いてしまった。彼は公文書・私文書偽造で生計を立てていたのだろうか。もっと過激かの「地面師たち」のような存在だったのだろうか。
文章に残っているからといって、それが全て真実・史実であるとは限らないのは研究者でなくても分かっていることだ。でも、椿井文書のようにここまで巧妙に作られると見抜くのは大変そう。さらには筆者も本書の冒頭で語っているが、研究者としては興味のある事柄を調べたいのであって、偽書だと分かってもわざわざそれを“報告”することはなく、読み捨てるだけだろう。それが第二・第三の“被害者”を生んでしまう。そんな二次・三次被害を未然に防いだろう筆者のこの研究の価値はかなり高いと思う。読み物としてとても面白かった本書だが、果たして学会の中ではこの研究はどのように評価されているのだろうか。
ブログで人気を上げ、アフィリエイトで儲けようという場合、Googleの検索結果で上位になれるようにがんばるというテクニック(いわゆる“SEO”という奴がある)がある。その技の一つとして「被リンク」がある。他のブログから参照されている(リンクが貼られている)数が多いほど、その記事の信頼度が高いと評価されるというものだ。椿井政隆のやっていたこともそれに似ている。一つの偽文書だけではすぐにバレてしまうので、その文書を参照している別の文書を複数作ったり、架空の登場人物を色々な文書に載せて信頼度を上げている。歴史を学んでいると、「人々の考えることって、昔も今も変わらないなぁ」と思うことが良くある。この椿井文書もまさにそれだ。もちろん、SEOテクニック使っているブログがインチキであると言っている訳ではないけど。
情報の海に溺れるな、フェイクニュースを見極めろ、って警告は今に始まったことではない。逆に、そろそろちゃんとしようぜと思ってしまう。そんな感想を持った一冊でした。
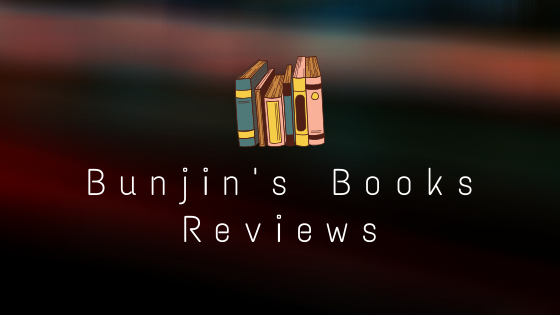



コメント