★あらすじ
生命の陸上起源説
「深海底の熱水噴出孔で生命は誕生した」というのが生命起源の説として現在は有力だ。しかし、そんな場所では生命に必要な物質がすぐに散逸してしまい、細胞膜や代謝系を形成することは難しい、という問題がある。
一方で、湿ったり(水が溜まったり)干上がったりを繰り返す陸上の間欠泉などの地熱帯では、乾燥期単純な分子から重合体が形成され、湿潤期には重合体が相互作用して脂肪酸で仕切られる構造が生まれる可能性がある。
生命爆発の導火線 エディアカラ生物の進化
複雑な多細胞生物はカンブリア爆発で生まれたと長年考えられてきた。しかし、シベリアやナミビアなどの最近の発見によってカンブリア爆発の数百万年前、先カンブリア時代末のエディアカラ紀にすでに複雑な動物が出現し始めていたことが示されている。
約5億5000万年前、アイスクリームのコーンを重ねたような形をした70mmほどの管状の骨格の化石「クロウディナ(Cloudina)」はナミビアを始め世界各地で見つかっている。さらにクロウディナは互いに固着し合って珊瑚のような礁を形成していた。
また、ナマポイキア(Namapoikia)は内骨格を持つ海綿動物の一種と思われ、クロウディナが形成した礁で生活していたらしい。このような新たな環境がカンブリア爆発につながっていったと考えられる。
サンショウウオは急がない 成功した逆張り生存戦略
人や犬、猫のゲノムサイズは30億2800万塩基対程度。カタツムリは9億3000万塩基対程度。それに対してサンショウウオの一種であるウイスウォータードッグは1180億塩基対もある。しかし、塩基対は多くても遺伝子が多いわけではない。サンショウウオのゲノムはトランスポゾンで溢れているのだ。
ゲノムサイズが大きいと細胞分裂のスピードが遅くなる。転写しなければならないゲノム量が多いからだ。結果、成長も遅くなる。結果としてサンショウウオは幼生のままで一生を過ごす。さらにある種のサンショウウオでは足の形成も中途半端で、指が生え揃わなかったり、後肢自体がない種もいる。多くのサンショウウオは脳も幼生型のままだ。
しかし、そのために未分化の肝細胞が体中に多く残っていると考えられ、結果として高度な再生能力を得た。四肢ばかりではなく、脳の1/4を失っても再生を果たすのだ。
★基本データ&目次
| 編集 | 日経サイエンス編集部 |
| 発行元 | 日経サイエンス(別冊日経サイエンス278) |
| 発行年 | 2025 |
| 副題 | 生物の型破りな戦略 |
| ISBN | 9784296123568 |
- Part 1 生命の起源に迫る
- 巨大ウイルスがゆるがす生物と無生物の境界
- 試験管で再現したRNA生命体の進化
- 生命の陸上起源説
- 地下にいた始原生命体
- Part 2 爆発的進化が起きた海
- 生命爆発の導火線 エディアカラ生物の進化
- 最古の左右相称動物 モンゴルで生痕化石を発見
- 深海で「新界」を発見
- Part 3 大絶滅を生き抜くヒント
- 微生物スライムがとどめを刺した古生代末の大絶滅
- 恐竜よりもしぶとい! 慎ましさで大絶滅を生き延びた哺乳類
- 南極の氷河期を生き延びたトビムシの謎
- Part 4 型破りな進化戦略
- サンショウウオは急がない 成功した逆張り生存戦略
- あなたなしでは生きていけない 昆虫と植物の強すぎる絆
- ヘビが手足を失ったわけ
- Part 5 進化は今も起きている
- 都市が変える生物進化
- 新種誕生の現場
- 都市の足元で起きている進化
★ 感想
これまでに雑誌 日経サイエンスに掲載された記事を再編集したムック本。常識となっている定説を覆す話や、そんな生物がいるのか(いたのか)という話が一杯で、とても興味深く読めた。
スティーヴン・ジェイ グールド の「ワンダフル・ライフ」に驚かされたのはもう何十年も前だ。そこから研究は進み、さらなる”ワンダフル”なことが溢れ出している感じだ。「熱水噴出孔 生命誕生説」への反論「周りが水だらけだから、必要な物質がすぐに散逸しちゃって生命誕生に至らない」という指摘は、言われてみればその通り。なんで今まで気が付かなかったのだろうと思えるほど。TVなどであのぶくぶくと黒煙を吐く噴出孔のビデオを見せれると、その周りには果てしない海が広がっていることが文字通り見えなくなっていたのだろう。「視野を広く持て」とはよく言われているはずなのだが。。。
「恐竜が隕石衝突で絶滅し、その後は哺乳類が”天下を取った”」というストーリーも確かに単純すぎる。衝突のあと、哺乳類も絶滅寸前までの状況に追い込まれ、九死に一生を得るような形でなんとか生き延びたということのようだ。もちろん、これは哺乳類全体を擬人化した言い方で、実際は哺乳類も殆どの種が絶滅してしまって、ほんの僅かの種がなんとか今につながる糸を残してくれたようだ。
さらにはCO2濃度の上昇、気温上昇によっても”簡単に”大絶滅が起きるという話の方がもっと恐ろしい。隕石の衝突が今すぐ起きる確率は小さそうだが、CO2濃度の上昇は「今、そこにある危機」だ。「歴史から学べ」だけでは足りず、我々は考古学・古生物学からも大いに学ばねばいけないようだ。気温が上昇すると、有毒物質を排出する菌・藻類が大繁殖し、淡水が汚染されて飲水がなくなるという話は眼の前で起き始めているのではないかと思える危機だ。
まあ、そんな教訓めいた話もあるが、単純に進化の話は面白い。”都会”という新たな環境下で起きている進化も興味深く、自分でも実際に確かめられそう。そんな楽しい話が一杯な本書は誰にでもおすすめできる一冊だ。
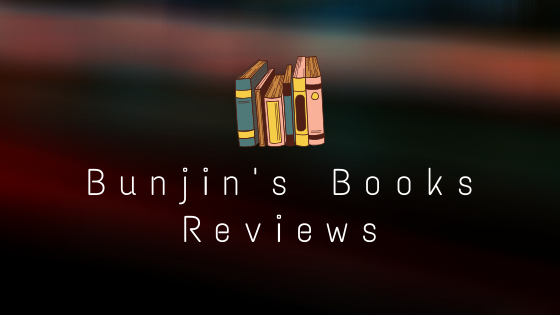



コメント