★あらすじ
「古事記」神代の巻の最初に登場するのが天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)、高御産巣日神(タカミムスビノカミ)、神産巣日神(カミムスビノカミか)。後世の「延喜式」などにはアメノミナカヌシを祀る神社は出てこない。記紀編纂者が作り出した思弁的な神であろう。
一方、タカミムスビとカミムスビは「生産」を表すムスの語に「神霊」を表すスがつき、「日本書紀」では産霊の字を当てているように万物を生み出す神々だ。「延喜式」にもこれら神を祀る多くの神社が記されている。タカミムスビは宮廷の大嘗祭の祭神であり、カミムスビと共に農耕を神格化したものだ。
太陽信仰は各地で個々にあったが、対馬のオヒデリサンは「日本書紀」にも「日神」と呼ばれる太陽神で、アマテラス女神の元になった神である。漁民の素朴な神に大和朝廷が着目し、皇室の氏神として仕立てたのだ。
古代エジプトの太陽神ラーは船に乗って空を旅した。スウェーデン、ブルターニュ、アイルランドでも太陽神の乗り物は船だ。「播磨風土記」では天照大神も船に乗っている。太陽の運行を、海を渡る船に見立てた訳だ。だが、この船や海に関係深い神が大和などの山間の盆地の人々から生まれるはずがない。
ヨーロッパでもオリエントでも、冬至は太陽が一旦死に、再び復活・再誕する日と考えられた。天照大神の天石屋戸の話も同様で、冬至の太陽祭儀を神話化したものだ。元来は伊勢の海人たちが伝えていた東南アジア系の太陽神祭儀が元になったのだろう。
★基本データ&目次
| 作者 | 松前健 |
| 発行元 | 吉川弘文館 (読みなおす日本史) |
| 発行年 | 2016 |
| ISBN | 9784642065979 |
- はしがき
- 世のはじめの神々
- 日・月二神とスサノヲの崇拝
- 高天原の神話
- 出雲神話の謎
- 二つのパンティオン
- 日向神話の世界
- 神武の東征
- 日本神話
- 日本神話の主な参考文献
- 『神々の系譜 日本神話の謎』を読む 平藤喜久子
★ 感想
「時の為政者が自己の政権の正当化のために神話を創る・改ざんする。征服した相手の神を自分たちの神話に取り込み、上下関係を明確化する。」といった辺りが、私が日本の神話に対して抱いていたイメージ。本書を読んで、話はそれほど単純なものではないことがまずもって良くわかった。
私が思っていたようなことももちろんあり、天皇(大王)一族を頂点に、物部氏や中臣氏などの豪族たちの氏神を色々と話しに組み込んでいったようだ。と言いつつ、庶民の土着の神たちの神話がベースになっていることもあり、かなり重層的に形づくられて行ったことがわかった。
しかも、比較神話学の手法で分析すると、アマテラスが岩戸に隠れた話や、黄泉の国に追放された荒ぶる神スサノヲの神話は北欧やら東南アジアやら中南米やら、各地に似たような神話が残っていて、普遍的な「太陽神」神話、「死者の国」神話と同系列と見做されるようだ。そしてさらに面白いのが、この“似ている”理由が、人間が持つ共通感覚(太陽を神聖なものとして崇めるなど)によるもの、つまりは直接の関係がない離れた土地でも同じ様な神話が語られる場合と、実際に人々の交流によって別の地の神話が伝わり、それが受容されることによって似てるけどそれぞれの地に合わせて変えられていったものがあることだ。古代日本では後者の場合も多いようで、南方の島々の人たちの神話が取り入れられたりしている。荒波をものともせずに行き来をしていた古代人のバイタリティには感心してしまう。逆に、神話の類似性からそんな交流があったことの傍証にもなっている訳だが。
その独自性と、世界各地と比較しての同質性と、当たり前だが両方を持ち合わせて形を成しているという、日本文化がどのように形成されていったのかの一端が神話を考えることを通して見ていけるのが面白かった。
「古事記」と「日本書記」という”二大古書”が内容に異なる部分が多いことが、「聖書」だけをまるまる信じる原理主義者のような存在を日本では産まなかったのではないかと思う。その違いの意味を探ることでこのように神話を”客観的”に分析していく下地ができたのだろう。宗教として神や神話を信じることと、それらを歴史・史実だと考えてしまうのとは大きな違いがある。
そんなことも本書を読みながら考えた。
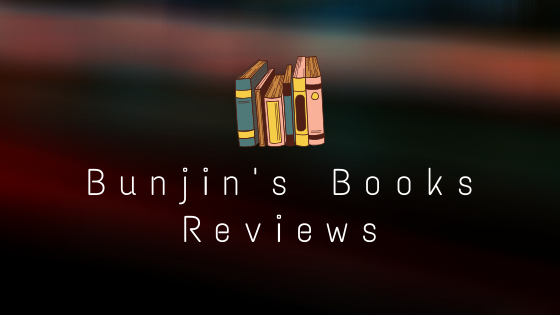



コメント